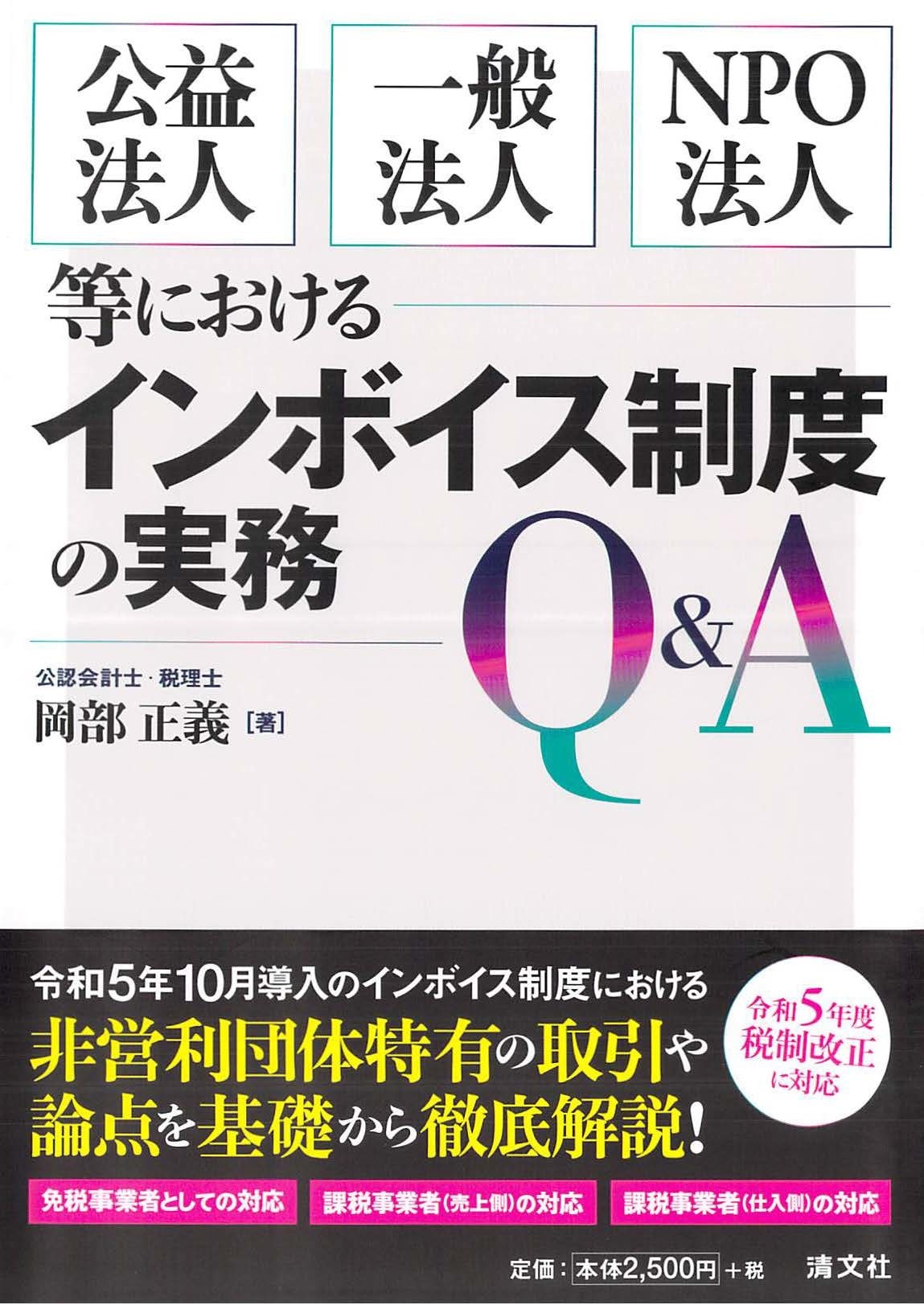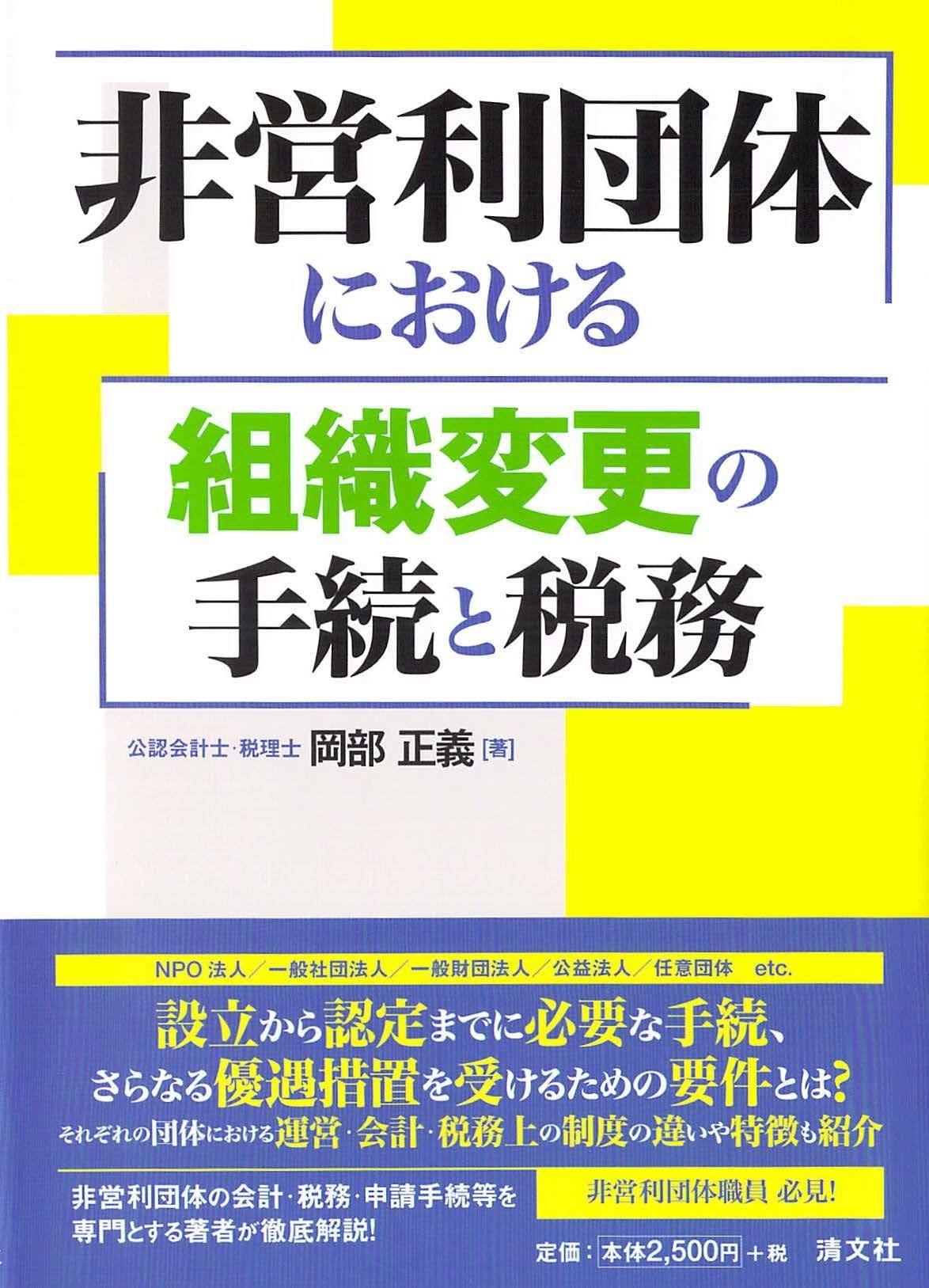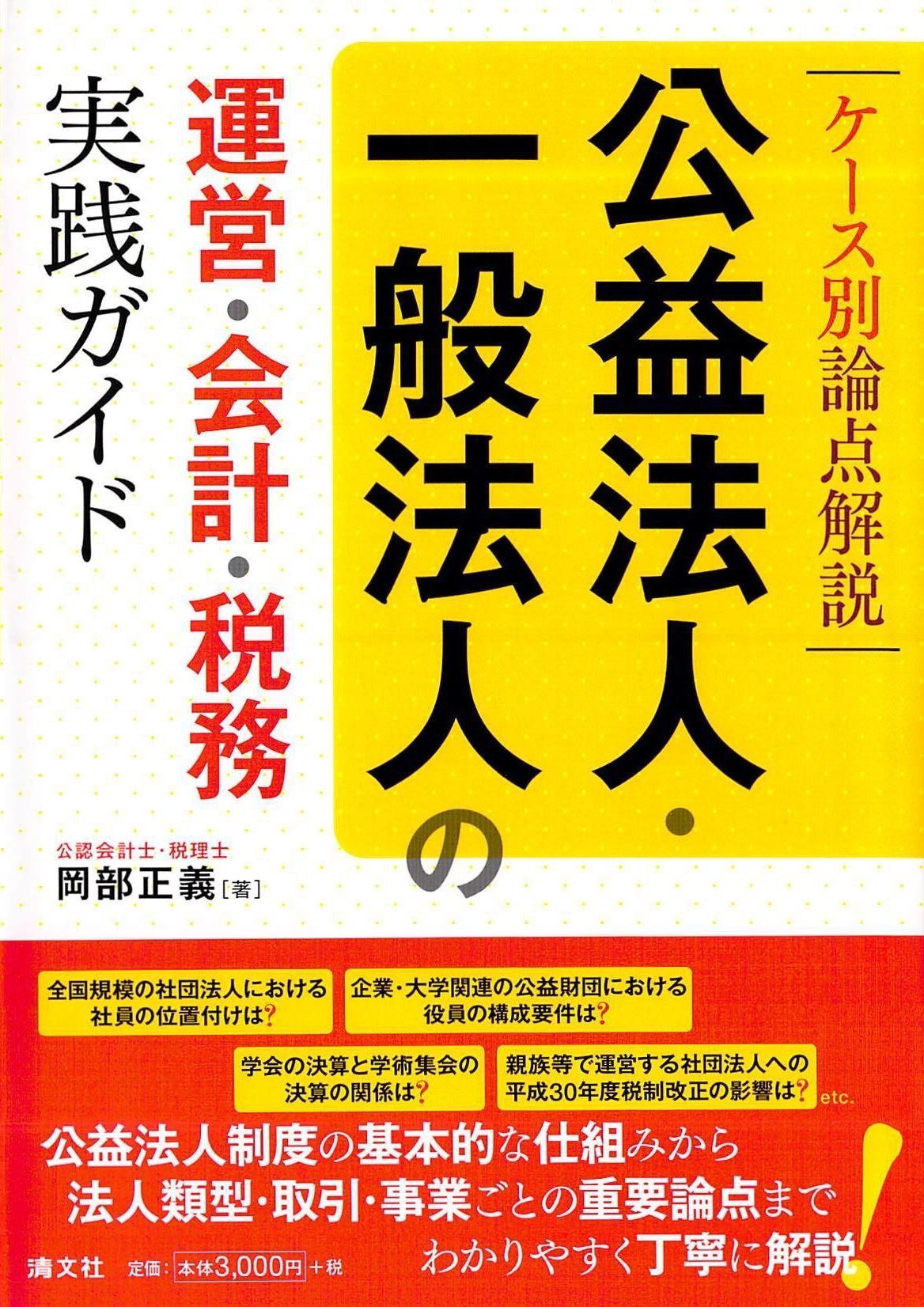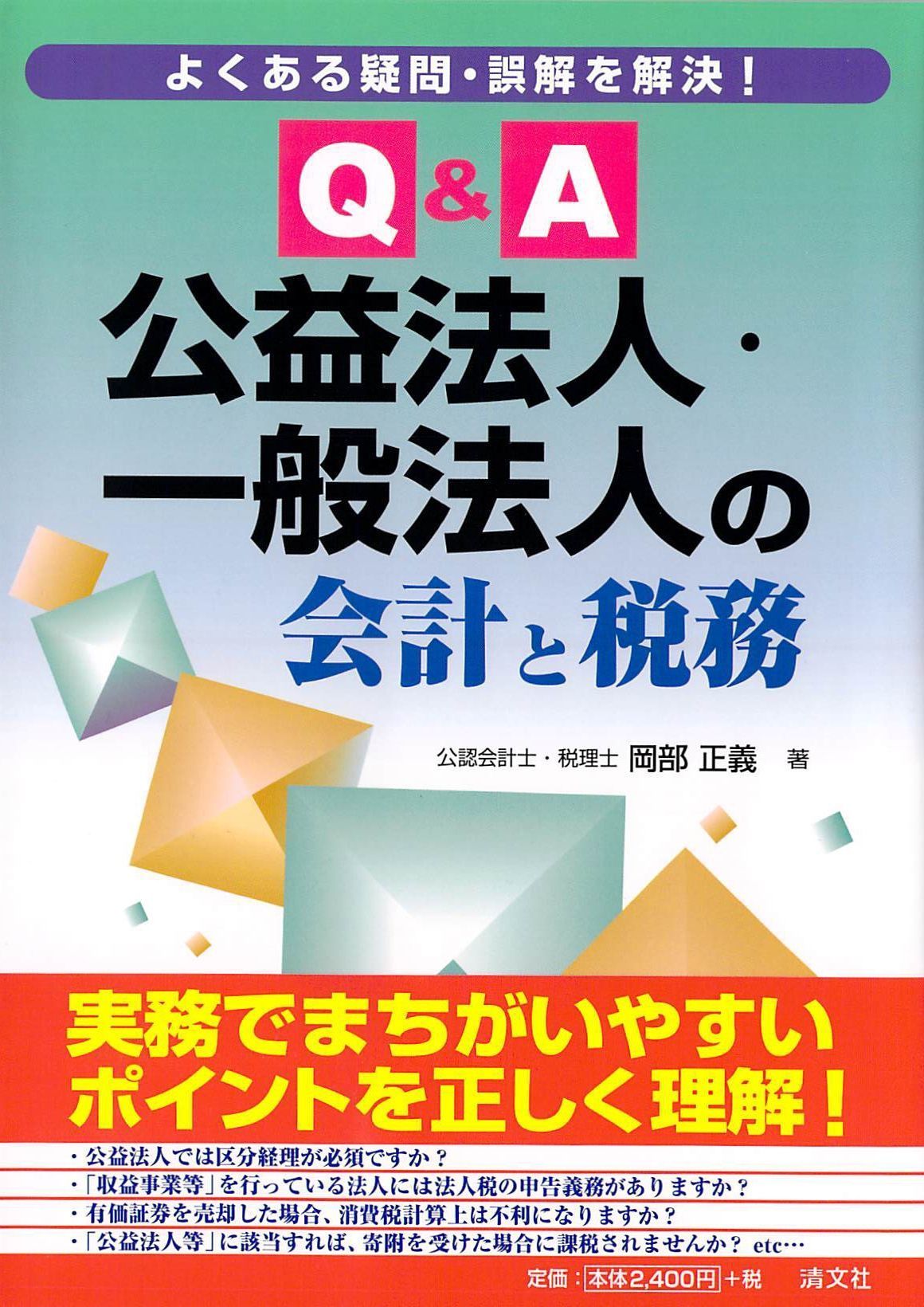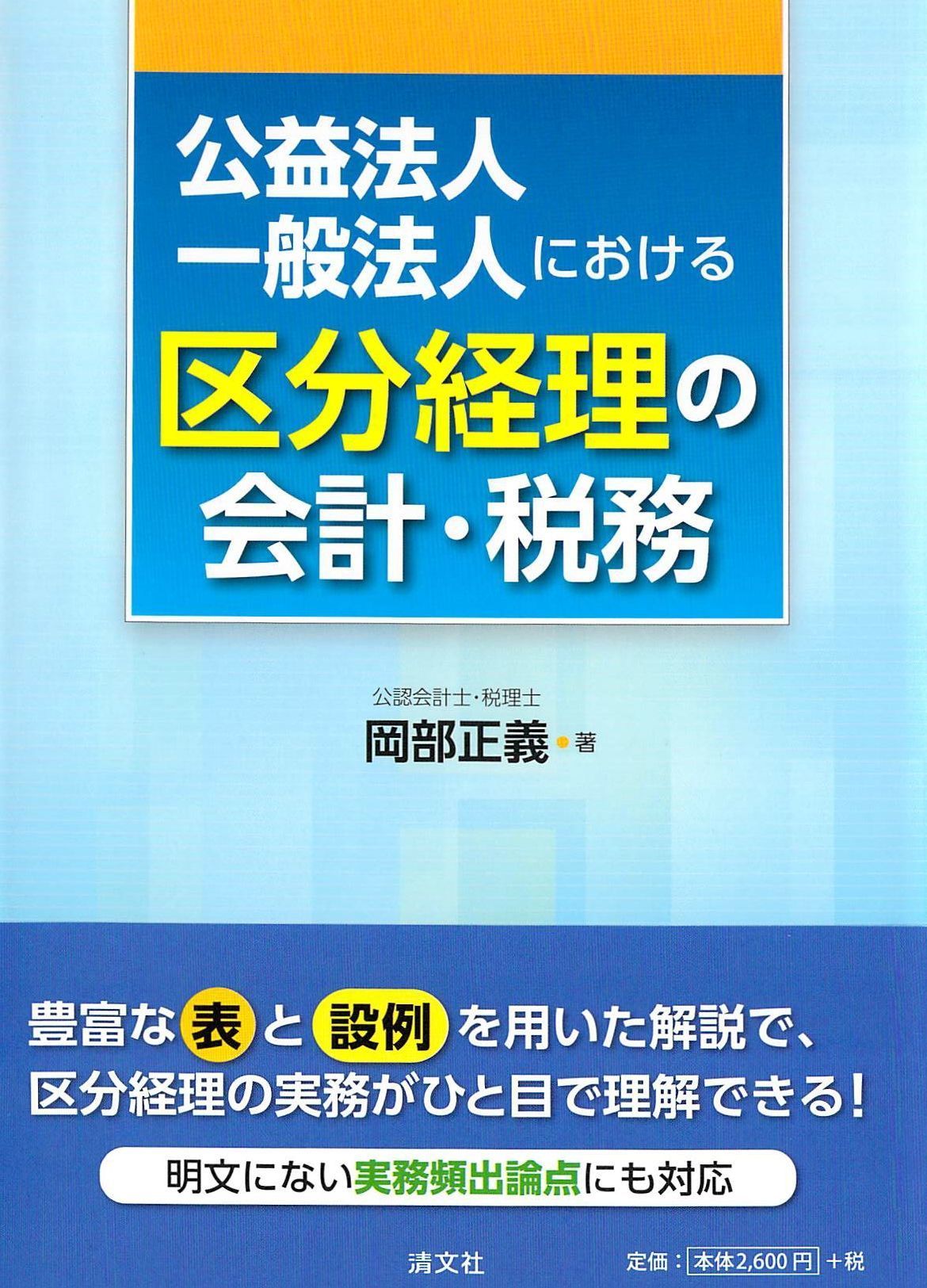学会(学術団体)の運営上・税務上の留意点
学会(学術団体)の運営上の留意点・税務上の留意点について解説します。
(運営上の留意点)
(税金論点:法人税の留意点)
(税金論点:消費税の留意点)
(その他税金)
(学術団体の組織変更論点)
一般法人で活動している学会(学術団体)を公益法人化すべきか否か
NPO法人で活動している学会(学術団体)を公益法人化すべきか否か
(その他)
任意団体は、法律で定められた組織ではなく、任意の組織であるため、基本的にその団体の定款・会則等で定められたルールに従って運営していれば問題ありません。
1.理事会の運営
定款・会則等で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
また、決議できる内容、開催回数、書面決議の有無等も定款・会則等で定めた内容に従うことになります。
2.総会の運営
定款・会則等で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
また、決議できる内容、開催回数、書面決議の有無等も定款・会則等で定めた内容に従うことになります。
3.委員会の運営
委員会の役割、委員の選任、任期等を定款・会則等に定めて運営することになります。
4.予算の承認
定款・会則等で定めた承認機関(理事会・総会等)で承認することになります。
5.決算の承認
定款・会則等で定めた承認機関(理事会・総会等)で承認することになります。
一般社団法人は、一般法に従って法人運営する必要があります。一般社団法人には、様々な機関設計のパターンがありますが、以下では最も一般的な理事会設置法人を前提として解説します。
1.理事会の運営
定款で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
なお、決算の承認、役員の選任・解任、定款の変更等の重要意思決定事項は、理事会での承認にすることはできません(たとえば、途中退任した理事の補充を理事会決議で行うことはできません)。
理事会への代理出席・書面決議は認められておりません。そのため、必ず本人が出席する必要があります。
また、監事は、理事会に出席する義務があります。ただし、監事の出席自体は理事会の決議要件とは関係ないため、仮に監事が欠席していたとしても、理事会自体は有効となります。
(監事の都合による理事会の欠席は、監事自身の任務懈怠の責任が問われることがあっても、理事会が成立しないということにはなりません。ただし、そもそも監事に対して招集手続をしていない結果、監事が欠席している場合は、理事会の招集手続き上の瑕疵により、理事会の決議に影響が生じる可能性があります)。
なお、書面決議は認められておりませんが、例外的に定款の定めをおけば、理事会の決議の省略を行うことができます。理事会の決議の省略とは、理事・監事が書面等で全員賛成していれば、理事会を物理的に開催しなくても、理事会の決議があったものとみなす規定です。
さらに、理事会は、意思決定の場だけでなく、代表理事・業務執行理事の業務執行の報告の場でもあります。そのため、原則として3ヵ月に1回は業務執行の報告を行う必要があります(定款の定めにより、年2回に省略することも可能)。
その他、決算承認、役員改選時における代表理事・業務執行理事の選任等は理事会が行う必要があります。
そのため、少なくとも年2回(役員改選時においては年3回)は、理事会を開催する必要があります。
(たとえば、①予算承認+報告、②決算承認+報告、③代表理事等の選任)
2.総会の運営
定款で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
総会は、社団法人における最高意思決定機関であり、決算承認は総会で行う必要があるため、必ず年1回は開催します。
総会は、理事会と異なり、代理人出席・書面決議等が認められております。
なお、総会においては、原則として招集通知の議題についてのみ決議ができるため、総会の場において、緊急動議により、招集通知にない議題を決議することはできません。
総会では、社員からの質問に理事・監事は答える必要があるため、理事・監事も出席することになります。
3.委員会の運営
委員会は、任意の機関であるため、定款等に定めれば、任意に設置することが可能です。ただし、委員会は法律上の機関ではないため、理事会・総会の決議事項としているような事項を任意の機関である委員会等に委任することは認められておりません。
4.予算の承認
予算の承認については法律上、特に定めはありません。そのため、理事会の承認、理事会の承認+総会の承認としても、いずれも問題ありません。
5.決算の承認
決算の承認は、監事監査を経た上で、理事会で承認を行い、その上で総会の承認が必要となります。
総会の開催日の2週間前から決算書類を事務所に備え置く必要があるため、決算承認理事会の開催日と総会の開催日は、2週間以上空けておく必要があります。
6.行政への対応
一般社団法人は、法律上の組織であるため、名称変更・住所変更・役員変更等を行った場合は、登記を行う必要があります。
なお、公益法人制度改革により旧来特例民法法人であった法人で一般社団法人に移行した法人のうち、公益目的支出計画を実施中の法人(移行法人)は、事業年度終了後3ヵ月以内に行政庁に対し、公益目的支出計画実施報告書を提出する必要があります。公益目的支出計画実施報告書は、監事監査及び理事会承認、総会報告の対象となります。
また、上記の移行法人は、実施事業等の内容に変更がある場合は、行政庁に対して変更手続を行う必要があります。
一般財団法人は、一般法に従って法人運営する必要があります。
1.理事会の運営
定款で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
なお、決算の承認、役員の選任・解任、定款の変更等の重要意思決定事項は、理事会での承認にすることはできません(たとえば、途中退任した理事の補充を理事会決議で行うことはできません)。
理事会への代理出席・書面決議は認められておりません。そのため、必ず本人が出席する必要があります。
また、監事は、理事会に出席する義務があります。ただし、監事の出席自体は理事会の決議要件とは関係ないため、仮に監事が欠席していたとしても、理事会自体は有効となります。
(監事の都合による理事会の欠席は、監事自身の任務懈怠の責任が問われることがあっても、理事会が成立しないということにはなりません。ただし、そもそも監事に対して招集手続をしていない結果、監事が欠席している場合は、理事会の招集手続き上の瑕疵により、理事会の決議に影響が生じる可能性があります)。
なお、書面決議は認められておりませんが、例外的に定款の定めをおけば、理事会の決議の省略を行うことができます。理事会の決議の省略とは、理事・監事が書面等で全員賛成していれば、理事会を物理的に開催しなくても、理事会の決議があったものとみなす規定です。
さらに、理事会は、意思決定の場だけでなく、代表理事・業務執行理事の業務執行の報告の場でもあります。そのため、原則として3ヵ月に1回は業務執行の報告を行う必要があります(定款の定めにより、年2回に省略することも可能)。
その他、決算承認、役員改選時における代表理事・業務執行理事の選任等は理事会が行う必要があります。
そのため、少なくとも年2回(役員改選時においては年3回)は、理事会を開催する必要があります。
(たとえば、①予算承認+報告、②決算承認+報告、③代表理事等の選任)
2.評議員会の運営
定款で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
評議員会は、財団法人における最高意思決定機関であり、決算承認は評議員会で行う必要があるため、必ず年1回は開催します。
評議員会も理事会同様、代理人出席・書面決議は認められておりません。
なお、評議員会においては、原則として招集通知の議題についてのみ決議ができるため、評議員会の場において、緊急動議により、招集通知にない議題を決議することはできません。
評議員会では、評議員からの質問に理事・監事は答える必要があるため、理事・監事も出席することになります。
3.委員会の運営
委員会は、任意の機関であるため、定款等に定めれば、任意に設置することが可能です。ただし、委員会は法律上の機関ではないため、理事会・評議員会の決議事項としているような事項を任意の機関である委員会等に委任することは認められておりません。
4.予算の承認
予算の承認については法律上、特に定めはありません。そのため、理事会の承認、理事会の承認+評議員会の承認としても、いずれも問題ありません。
5.決算の承認
決算の承認は、監事監査を経た上で、理事会で承認を行い、その上で評議員会の承認が必要となります。
評議員会の開催日の2週間前から決算書類を事務所に備え置く必要があるため、決算承認理事会の開催日と評議員会の開催日は、2週間以上空けておく必要があります。
6.行政への対応
一般財団法人は、法律上の組織であるため、名称変更・住所変更・役員変更等を行った場合は、登記を行う必要があります。
なお、公益法人制度改革により旧来特例民法法人であった法人で一般財団法人に移行した法人のうち、公益目的支出計画を実施中の法人(移行法人)は、事業年度終了後3ヵ月以内に行政庁に対し、公益目的支出計画実施報告書を提出する必要があります。公益目的支出計画実施報告書は、監事監査及び理事会承認、評議員会報告の対象となります。
また、上記の移行法人は、実施事業等の内容に変更がある場合は、行政庁に対して変更手続を行う必要があります。
公益社団法人は、一般法に従って法人運営する必要があります。
1.理事会の運営
定款で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
なお、決算の承認、役員の選任・解任、定款の変更等の重要意思決定事項は、理事会での承認にすることはできません(たとえば、途中退任した理事の補充を理事会決議で行うことはできません)。
理事会への代理出席・書面決議は認められておりません。そのため、必ず本人が出席する必要があります。
また、監事は、理事会に出席する義務があります。ただし、監事の出席自体は理事会の決議要件とは関係ないため、仮に監事が欠席していたとしても、理事会自体は有効となります。
(監事の都合による理事会の欠席は、監事自身の任務懈怠の責任が問われることがあっても、理事会が成立しないということにはなりません。ただし、そもそも監事に対して招集手続をしていない結果、監事が欠席している場合は、理事会の招集手続き上の瑕疵により、理事会の決議に影響が生じる可能性があります)。
なお、書面決議は認められておりませんが、例外的に定款の定めをおけば、理事会の決議の省略を行うことができます。理事会の決議の省略とは、理事・監事が書面等で全員賛成していれば、理事会を物理的に開催しなくても、理事会の決議があったものとみなす規定です。
さらに、理事会は、意思決定の場だけでなく、代表理事・業務執行理事の業務執行の報告の場でもあります。そのため、原則として3ヵ月に1回は業務執行の報告を行う必要があります(定款の定めにより、年2回に省略することも可能)。
その他、決算承認、役員改選時における代表理事・業務執行理事の選任等は理事会が行う必要があります。
そのため、少なくとも年2回(役員改選時においては年3回)は、理事会を開催する必要があります。
(たとえば、①予算承認+報告、②決算承認+報告、③代表理事等の選任)
2.総会の運営
定款で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
総会は、社団法人における最高意思決定機関であり、決算承認は総会で行う必要があるため、必ず年1回は開催します。
総会は、理事会と異なり、代理人出席・書面決議等が認められております。
なお、総会においては、原則として招集通知の議題についてのみ決議ができるため、総会の場において、緊急動議により、招集通知にない議題を決議することはできません。
総会では、社員からの質問に理事・監事は答える必要があるため、理事・監事も出席することになります。
3.委員会の運営
委員会は、任意の機関であるため、定款等に定めれば、任意に設置することが可能です。ただし、委員会は法律上の機関ではないため、理事会・総会の決議事項としているような事項を任意の機関である委員会等に委任することは認められておりません。
4.予算の承認
予算の承認については法律上、特に定めはありません。そのため、理事会の承認、理事会の承認+総会の承認としても、いずれも問題ありません。
5.決算の承認
決算の承認は、監事監査を経た上で、理事会で承認を行い、その上で総会の承認が必要となります。
総会の開催日の2週間前から決算書類を事務所に備え置く必要があるため、決算承認理事会の開催日と総会の開催日は、2週間以上空けておく必要があります。
6.行政への対応
公益社団法人は、法律上の組織であるため、名称変更・住所変更・役員変更等を行った場合は、登記を行う必要があります。
公益社団法人は、行政庁の監督下にあるため、事業年度開始の前までに事業計画・収支予算書を、事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告等を行政庁に提出する必要があります。
また、事業内容の変更、役員変更等、法人運営に関する変更が生じたときには、行政庁に対して、変更手続を行う必要があります。
公益財団法人は、一般法に従って法人運営する必要があります。
1.理事会の運営
定款で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
なお、決算の承認、役員の選任・解任、定款の変更等の重要意思決定事項は、理事会での承認にすることはできません(たとえば、途中退任した理事の補充を理事会決議で行うことはできません)。
理事会への代理出席・書面決議は認められておりません。そのため、必ず本人が出席する必要があります。
また、監事は、理事会に出席する義務があります。ただし、監事の出席自体は理事会の決議要件とは関係ないため、仮に監事が欠席していたとしても、理事会自体は有効となります。
(監事の都合による理事会の欠席は、監事自身の任務懈怠の責任が問われることがあっても、理事会が成立しないということにはなりません。ただし、そもそも監事に対して招集手続をしていない結果、監事が欠席している場合は、理事会の招集手続き上の瑕疵により、理事会の決議に影響が生じる可能性があります)。
なお、書面決議は認められておりませんが、例外的に定款の定めをおけば、理事会の決議の省略を行うことができます。理事会の決議の省略とは、理事・監事が書面等で全員賛成していれば、理事会を物理的に開催しなくても、理事会の決議があったものとみなす規定です。
さらに、理事会は、意思決定の場だけでなく、代表理事・業務執行理事の業務執行の報告の場でもあります。そのため、原則として3ヵ月に1回は業務執行の報告を行う必要があります(定款の定めにより、年2回に省略することも可能)。
その他、決算承認、役員改選時における代表理事・業務執行理事の選任等は理事会が行う必要があります。
そのため、少なくとも年2回(役員改選時においては年3回)は、理事会を開催する必要があります。
(たとえば、①予算承認+報告、②決算承認+報告、③代表理事等の選任)
2.評議員会の運営
定款で定めた定足数・議決権の要件に従って、運営することになります。
評議員会は、財団法人における最高意思決定機関であり、決算承認は評議員会で行う必要があるため、必ず年1回は開催します。
評議員会も理事会同様、代理人出席・書面決議は認められておりません。
なお、評議員会においては、原則として招集通知の議題についてのみ決議ができるため、評議員会の場において、緊急動議により、招集通知にない議題を決議することはできません。
評議員会では、評議員からの質問に理事・監事は答える必要があるため、理事・監事も出席することになります。
3.委員会の運営
委員会は、任意の機関であるため、定款等に定めれば、任意に設置することが可能です。ただし、委員会は法律上の機関ではないため、理事会・評議員会の決議事項としているような事項を任意の機関である委員会等に委任することは認められておりません。
4.予算の承認
予算の承認については法律上、特に定めはありません。そのため、理事会の承認、理事会の承認+評議員会の承認としても、いずれも問題ありません。
5.決算の承認
決算の承認は、監事監査を経た上で、理事会で承認を行い、その上で評議員会の承認が必要となります。
評議員会の開催日の2週間前から決算書類を事務所に備え置く必要があるため、決算承認理事会の開催日と評議員会の開催日は、2週間以上空けておく必要があります。
6.行政への対応
公益財団法人は、法律上の組織であるため、名称変更・住所変更・役員変更等を行った場合は、登記を行う必要があります。
公益財団法人は、行政庁の監督下にあるため、事業年度開始の前までに事業計画・収支予算書を、事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告等を行政庁に提出する必要があります。
また、事業内容の変更、役員変更等、法人運営に関する変更が生じたときには、行政庁に対して、変更手続を行う必要があります。
学会(学術団体)が毎年度開催する学術集会について、以下のように運営しているケースがよく見受けられます。
①毎年学術集会を主宰する役員(委員)を選出する。
②学術集会の運営は、学会本体の事務局ではなく、主宰する役員(委員)が所属する研究機関(大学)等が行う。
③具体的な学術集会の事務運営は、別途学術運営を代行する民間会社に委託する。(主宰者により、委託する民間会社も毎年異なる。)
④学会本体からは、補助金等を支出するが、学術集会全体の収入・支出は、学会本体の決算には取り込んでいない。
上記のような運営を行っている場合、当該学術集会の収支は、学会本体に合算すべきか否か、議論があるところです。
学術集会自体が、学会本体とは独立した組織(任意団体)として捉えた場合、学会本体に収支を合算することはありませんが、学術集会が、学会本体の活動の一部として捉えた場合、学会本体に収支を合算すべきであるといえます。
特に、公益法人の場合、認定基準である財務上の基準にも影響を及ぼすことから、学術集会の収支の取扱いについては、行政庁と相談の上、慎重に対応することが求められます。
また、公益法人以外であっても、学術集会の収支を学会本体に合算するか否かによって、課税の範囲が異なってしまうことから、所轄税務署と相談の上、慎重に対応することが求められます。
全国組織の学会(学術団体)の場合、地方毎に支部組織を有している場合があります。
支部組織には様々な形態があり、単なる連絡組織としての支部組織を置いている場合と、支部自体で事業活動を行い、支部自体に収支が発生する場合があります。
支部自体で事業活動を行い、支部自体で収支が発生する場合、当該収支を学会本体に合算しているか否かが議論となります。この場合、支部が学会の組織の一部か否かで考えることになります。
仮に支部が学会の組織の一部であると考えると、支部の収支を学会本体に取り込まなければなりません。他方、支部は学会本体とは別の組織(任意団体)であると考えると、支部の収支を学会本体に取り込む必要はありません。なお、学会本体とは別の組織(任意団体)であると考える場合、学会本体とは、別であることが分かるように一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人等の名称を支部に付けることは認められておりません。
(例)
一般社団法人A学会 関東支部 → 一般社団法人A学会の組織の一部
A学会 関東支部 → 一般社団法人A学会とは別の組織(任意団体)
法人税の申告義務の有無は、法人の類型及び収益事業の有無によって決まります。
公益的な活動を行っているから申告義務がない、法人全体が赤字なので申告義務がない、任意団体だから申告義務がない、ということにはなりません。
まず、法人税の申告義務の有無については、大きく以下の2つに分かれます。
1.全所得課税の法人
①非営利型法人以外の一般社団法人
②非営利型法人以外の一般財団法人
上記の法人は、必ず法人税の申告義務があり、通常の株式会社と課税範囲は変わりません。そのため、法人におけるすべての収益・費用は課税の範囲に含まれます。たとえ、寄附金・会費収入等の収入項目であったとしても、課税の範囲に含まれます。
非営利型法人の要件とは、以下の通りです。通常、一般法人の学会(学術団体)は、非営利型法人を選択しているケースが多いため、全所得課税の法人は少ないと思われます。
(非営利型法人の要件)
非営利型法人には、「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2つがあります。
(非営利性が徹底された法人とは)
非営利性が徹底された法人とは、以下の4つの要件を満たした法人のことをいいます。
| 1 | 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること |
| 2 | 定款に解散時の残余財産が公益社団・財団法人等の一定の公益的な団体に帰属する旨の定めがあること |
| 3 | 1、2の要件にある定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと(特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと) |
| 4 | 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること |
(共益的活動を目的とする法人とは)
共益的活動を目的とする法人とは、以下の7つの要件を満たした法人のことをいいます。
| 1 | 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること |
| 2 | 定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること |
| 3 | 主たる事業として収益事業を行っていないこと |
| 4 | 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと |
| 5 | 定款に解散時の残余財産が特定の個人又は団体(一定の公益的な団体等を除く。)に帰属する旨の定めがないこと |
| 6 | 特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと |
| 7 | 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること |
2.収益事業課税の法人・団体
①任意団体
②非営利型法人の一般社団法人
③非営利型法人の一般財団法人
④公益社団法人
⑤公益財団法人
上記の法人・団体は、収益事業課税となります。収益事業課税の場合、収益事業のみ課税されることになります。そのため、収益事業がない法人は、法人税の申告義務がなく、収益事業がある法人は、法人の事業のうち、収益事業部分のみを計算して法人税の申告を行うことになります。
収益事業とは、法人税法施行令5条1項に限定列挙される34の事業を継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
| 物品販売業 | 請負業 | 仲立業 | 遊覧所業 |
| 不動産販売業 | 印刷業 | 問屋業 | 医療保険業 |
| 金銭貸付業 | 出版業 | 鉱業 | 技芸教授業 |
| 物品貸付業 | 写真業 | 土石採取業 | 駐車場業 |
| 不動産貸付業 | 席貸業 | 浴場業 | 信用保証業 |
| 製造業 | 旅館業 | 理容業 | 無体財産権提供業 |
| 通信業 | 料理店業その他飲食店業 | 美容業 | 労働者派遣業 |
| 運送業 | 周旋業 | 興行業 |
|
| 倉庫業 | 代理業 | 遊技所業 |
|
なお、公益社団法人・公益財団法人の場合、仮に上記の34の事業に該当していたとしても、公益目的事業に該当する事業は、収益事業の範囲から除外されております。そのため、公益社団法人・公益財団法人の場合、課税の範囲がより限定されています。
1.入会金・会費の考え方について
入会金・会費は、収益事業の事業収入ではないため、収益事業に該当しません。
なお、会費であっても、通常の年会費のような会費とは異なり、事業の対価として収受する会費の場合、当該事業が収益事業に該当するか否かで判定することになります。
2.金融資産の運用収益について
金融資産の運用収益については、収益事業に区分されている資産から生じる運用益の場合、収益事業に含まれますが、それ以外の場合は収益事業に含まれません。
3.研修会の考え方について
講習会、研修会等は、技芸の教授に該当するか否かで、収益事業か否かを判定します。技芸の教授となる技芸の種類は、以下の22種類です。
| 洋裁 | 和裁 | 着物着付け | 編物 |
| 手芸 | 料理 | 理容 | 美容 |
| 茶道 | 生花 | 演劇 | 演芸 |
| 舞踊 | 舞踏 | 音楽 | 絵画 |
| 書道 | 写真 | 工芸 | デザイン |
| 自動車操縦 | 小型船舶操縦 |
|
|
上記以外の内容で講習会、研修会を行う場合、例えば、医学系の講習会・研修会を実施したとしても、収益事業には該当しません。そのため、学会(学術団体)の研修会・講習会は、収益事業に該当しないケースが多いと思われます。
4.学術集会の考え方について
学術集会においては、シンポジウムやセミナー等を開催し、協賛する企業の展示ブース等があるのが一般的です。また、学術集会に関連する収入としては、参加料収入、展示料収入、抄録集の販売収入、広告収入等がよくある収入と思われます。
学術集会の行っている内容が収益事業に該当するか否かは、一つ一つの内容で判断していくことになります。
①参加料収入
参加料収入について、当該参加料がシンポジウム・セミナー等の参加費としての性格を有していると考えられる場合、研修会と同様、シンポジウム・セミナーの内容が技芸の教授に該当する内容か否かで判断します。例えば、医学系のシンポジウム・セミナーの参加費の場合、収益事業には該当しません。
②展示料収入
展示料収入については、原則として収益事業の席貸業に該当する可能性が高いといえます。
③抄録集の販売収入
抄録集の販売収入については、原則として、収益事業の出版業に該当する可能性が高いといえます。
④広告収入
広告収入は、それ自体が34の収益事業に該当しないため、収益事業に該当するか否かは、当該広告収入がどの事業の付随収入としての性格を有するかで判断します。すなわち、広告の元となる事業自体が税法上の収益事業に該当しない場合、付随収入である広告収入も収益事業に該当しませんが、広告の元となる事業自体が収益事業に該当した場合、付随収入である広告収入も収益事業に該当することになります。
5.会報(学会誌)等の考え方について
会報(学会誌)等が収益事業の出版業に該当するか否かは、ケースバイケースで判断することになります。
以下のような場合、会報(学会誌)等は収益事業の出版業から除外されることになります。
(1)特定資格会員向けの会報(学会誌)等
医師、弁護士、建築士等、特定の資格を会員とする法人が、会報等を主として会員に配布している場合は、収益事業から除外されます。なお、会報等とはあくまで主として会員だけに必要とされる記事を内容とする出版物であり、書店等で通常販売されるような内容のものは会報等には該当しません。また、主として会員に配布しているとは、8割程度を会員に頒布していることをいいます。なお、会員以外に無償で配布したものは会員に配布したものとして取扱います。
(2)学術等の会報(学会誌)等
学術を目的とする法人がその目的を達成するため会報等をもっぱら会員に配布している場合、収益事業から除外されます。なお、もっぱら会員に配布するとは、主として会員に配布している場合と異なり、会員だけに配布することをいいます。なお、会員以外に無償で配布したものは会員に配布したものとして取扱います。
なお、出版業に該当する出版物の対価を会費という名目で徴収していた場合、年会費という名目であったとしても、課税の対象となります。
また、学会誌等への広告収入が収益事業に該当するか否かは、当該学会誌等が収益事業に該当するか否かで判断することになります。
6.専門書籍の出版について
専門書籍の出版収入は、原則として出版業に該当する可能性が高いといえます。
7.ロイヤリティ収入の考え方について
ロイヤリティ収入は、原則として無体財産権の提供業に該当する可能性が高いといえます。
8.広告収入の考え方について
広告収入は、それ自体が34の収益事業に該当しないため、収益事業に該当するか否かは、当該広告収入がどの事業の付随収入としての性格を有するかで判断します。すなわち、広告の元となる事業自体が税法上の収益事業に該当しない場合、付随収入である広告収入も収益事業に該当しませんが、広告の元となる事業自体が収益事業に該当した場合、付随収入である広告収入も収益事業に該当することになります。
9.認定資格制度の考え方について
資格の認定自体は、技芸の教授に該当するか否かで判定します。技芸の教授に関連した資格の場合、収益事業に該当しますが、技芸の教授に関連しない資格の場合、収益事業に該当しません。
技芸の教授に関連するか否かは、「研修会の考え方」をご参照ください。
10.研究請負の考え方について
研究請負は、原則として請負業に該当する可能性が高いといえます。ただし、実費弁償契約等の場合、一定の要件を満たせば、請負業から除外できる場合もあります。
消費税は、原則として国内で行う対価性がある取引に対して課せられる税金です。
消費税の申告義務があるか否かは、原則として2事業年度前の課税売上高が10百万円を超えるか否かで判定します。
(なお、上記に該当しなかったとしても、前年の上半期の課税売上及び人件費が10百万円を超える場合も申告義務が生じます。また、自ら課税事業者を選択した場合も申告義務が生じます。)
消費税の申告義務と法人税の申告義務は全く連動しないので注意が必要です。法人税の申告義務はあるが、消費税の申告義務はないケース、逆に法人税の申告義務はないが、消費税の申告義務はあるケース等、状況によってケースバイケースです。また、法人全体が赤字だから、納税が発生しないというわけではないため、注意が必要です。
消費税の申告義務の有無、計算方法については、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、任意団体で特に違いはありません。そのため、いずれの法人・団体であったとしても、過去の課税売上高の大きさ等によって、申告義務の有無が分かれます。
収入の金額が課税売上に該当するか否かが申告義務の有無及び実際に消費税の計算をする上でも重要であると言えます。法人税上の収益事業に該当するか否かと、消費税上の課税取引に該当するか否かは、全く異なる判断基準であり、全く連動しないので留意が必要です。
以下、課税取引に該当するか否かについて解説します(以下、国内取引を前提として解説します)。
1.入会金・会費の考え方について
入会金・会費収入は、一般的には課税取引に該当しません。なお、会費収入であっても、通常の年会費と異なり、事業の対価としての性格を有している場合は、課税取引に該当する可能性があります(ある事業の参加料を会費として徴収している場合、課税取引に該当する可能性があります)。
2.金融資産の運用収益について
金融資産の運用収益は、課税取引には該当しません。
3.研修会の考え方について
研修会の参加収入は、対価性があるため、課税取引に該当します。
4.学術集会の考え方について
学術集会においては、シンポジウムやセミナー等を開催し、協賛する企業の展示ブース等があるのが一般的です。また、学術集会に関連する収入としては、参加料収入、展示料収入、抄録集の販売収入、広告収入等がよくある収入と思われます。
学術集会の行っている内容が課税取引に該当するか否かは、一つ一つの内容で判断していくことになります。
①参加料収入
参加料収入について、当該参加料がシンポジウム・セミナー等の参加費としての性格を有していると考えられる場合、対価性があるため、課税取引に該当します(会員の参加費については、学会活動の一環であるため、不課税として処理する場合もあります)。
②展示料収入
展示料収入については、対価性があるため、課税取引に該当します。
③抄録集の販売収入
抄録集の販売収入については、対価性があるため、課税取引に該当します。
④広告収入
広告収入は、対価性があるため、課税取引に該当します。
5.学会誌(会報)の考え方について
有償で頒布している場合、有償頒布部分は、課税取引に該当します。
また、会費収入として徴収している場合も、実質的に購読料の対価としての性格を有している場合、課税取引に該当します。
6.ロイヤリティ収入の考え方について
ロイヤリティ収入は、対価性があるため、課税取引に該当します。
7.専門書籍の出版について
専門書籍の出版収入は、対価性があるため、課税取引に該当します。
8.広告収入の考え方について
広告収入は、対価性があるため、課税取引に該当します。
9.認定資格制度の考え方について
資格認定の際の収入は、対価性があるため、課税取引に該当します。
10.研究請負の考え方について
研究請負は、対価性があるため、課税取引に該当します。
源泉徴収制度とは、法人・団体が給与の支払いや謝金の支払いをする場合に、所得税の一部を預かって、前もって国に納付する制度のことをいいます。
源泉徴収義務者は、原則として、支払いの翌月10日までに源泉税を納付する必要がありますが、給与の支払い人数が10人未満の小規模の法人・団体の場合は、納期の特例が認められていて、一定の手続きを行えば、給与の源泉納付を年2回(1月20日・7月10日)とすることも可能です。
なお、研修会の講師や機関誌の原稿の執筆者に対して、謝礼を支払う場合も源泉徴収が必要となりますが、当該源泉徴収は、給与の源泉納付とは異なり、翌月10日までに源泉税を納付する必要があります。
なお、謝礼について、本人に支払う手取額をきりのよい数値で支払う場合、源泉徴収金額を逆算して計算し、納付する必要があります。
たとえば、100,000円の謝礼(講師謝礼・原稿執筆謝礼)を手取額として支払う場合、源泉税率は、復興税を含めて10.21%となるので、以下のような計算を行います。
100,000円÷(1−10.21%)=111,370円
111,370円×10.21%=11,370円
謝礼としては、111,370円となり、源泉税11,370円を差し引いた100,000円を本人に支払い、11,370円は、源泉税として支払いの翌月10日までに国に納付することになります。
(謝礼を受け取った方の確定申告の計算上は、111,370円を報酬、11,370円を源泉徴収税額として計算することになります。)
なお、仮に現金ではなく、商品券等で報酬を支払ったとしても、現金で支払ったものと同様に上記のような計算を行い、源泉税を納付する必要があります。
任意団体で活動している学会(学術団体)を法人化すべきか否か検討する場合、メリット・デメリットを比較検討することになります。
メリットとしては、法人格を取得することで法人名義の契約が可能となり、社会的信頼性が高まることが挙げられます。
他方、デメリットとしては、法人運営に関して、法律上の規制を受けるため、従来よりも柔軟な団体運営ができないことが挙げられます。
法人化する場合、NPO法人と一般社団法人の選択肢があります。
|
| NPO法人 | 一般社団法人 |
| 設立手続 | 所轄庁の認証があるため、4か月程度必要。 | 定款認証と設立登記のみで簡単に設立可能。 |
| 行政からの監督 | あり。 | なし。 |
| 役員報酬 | 人数制限あり。 | 人数制限なし。 |
| 理事会運営 | 代理出席、書面決議も可能。 | 本人出席が必須。代理出席、書面決議不可。 |
| 役員の選任 | 総会以外でも選任可能。 | 社員総会で選任。 |
なお、一般法人が簡単に設立可能となったのは、平成20年12月以降であり、それ以前は、社団法人・財団法人を設立するのは容易ではありませんでした。そのため、それ以前に法人化する場合は、NPO法人で設立しているケースが多かったといえます。
しかしながら、平成20年12月以降は、簡単に一般法人を設立することが可能となりました。そのため、平成20年12月以降設立する法人は、設立が簡単であり、行政の監督を受けない一般法人の方が多いといえます。また、NPO法人は、一般的にボランティア団体としてのイメージが強いため、学術団体としては一般社団法人を選択するというケースが多いといえます。
なお、任意団体、NPO法人、一般社団法人(非営利型法人)について、法人税・消費税・源泉所得税の取扱いに大きな違いはありません。そのため、法人税・消費税・源泉所得税の観点からは、いずれの組織形態も大きな違いはありません。
任意団体で活動している学術団体が法人化を目指すケースとしては、団体の規模が大きくなり、法人化により権利義務関係を明確にした方が望ましいと考えられるケース、公的機関等から受託事業・補助金事業を受ける場合において、契約上、法人化が必要とされるケースがあります。
一般法人で活動している学会(学術団体)を公益法人化すべきか否か検討する場合、メリット・デメリットを比較検討することになります。
メリットとしては、社会的信頼性の向上と税務上の優遇措置が挙げられます。
他方、デメリットとしては、行政庁の監督下となり、認定法に定める様々な規制を受けることが挙げられます。
なお、公益法人となるためには、事前の準備と行政庁の審査を合わせて、年単位で時間がかかるのが一般的です。また、公益法人が一般法人に戻る場合、公益的な財産を国等に贈与しなければなりません。そのため、公益法人化すべきか否かは、慎重に検討する必要があります。
公益法人化の検討に際しては、一般的に言われているメリット・デメリットが、当団体のメリット・デメリットに該当するか個別具体的に検討する必要があります。
1.一般的なメリット・社会的信頼性の向上
一般的に公益法人は、社会的信頼性が高い法人といえます。他方、学術団体の場合、法人形態にかかわらず、社会的信頼性が高いケースが一般的です。そのため、改めて対外的に公益法人の肩書きが重要となるのはそれほど多くないかもしれません。
2.一般的なメリット・税務上の優遇措置
(1)寄付金の優遇措置
公益法人は、寄付する側にとって税制上の優遇措置があるため、寄付を受けやすくなるというメリットがあります。他方、法人の財源として、寄付金収入がそれほど重要でないケース、寄付金の優遇措置の有無に関係なく、寄付金が集まるケースがあるため、寄付金の優遇措置が学術団体にとってメリットとなるか否かはケースバイケースであると考えます。
(2)源泉所得税の優遇措置
公益法人は、利子等の源泉所得税が非課税となります。そのため、基本財産・特定資産等の運用益が大きい団体にとって、非課税措置となるか否かは、税務上重要となります。
他方、基本財産・特定資産等の運用益がそれほど大きくない団体にとっては、源泉所得税の優遇措置は、それほど重要でないといえます。
(3)法人税法上の優遇措置
公益法人も非営利型の一般社団法人もいずれも法人税法上の収益事業に課税されますが、公益法人の場合、より収益事業の課税範囲が限定されます。また、公益法人に関しては、収益事業から生じた利益を公益目的事業に繰入した場合、みなし寄付金が適用され、課税所得計算上、有利となります。
他方、学術団体の中には、法人税法上の収益事業を全く行っていないケース、法人税法上の収益事業は行っているが、課税所得がそもそも生じていないケースがあります。そのようなケースにおいては、そもそも法人税が生じていないため、法人税法上の優遇措置はあまり関係ないといえます。
(4)消費税の優遇措置
公益法人・一般法人は、寄付金収入・会費収入等の割合が大きい場合、消費税法上、特別な調整計算を行います。その際、寄付金収入の割合が大きい法人については、調整計算上、不利に働きます。
他方、平成25年度税制改正によって、公益法人の受ける寄付金のうち一定の要件を満たす寄付金に関しては、調整計算上、不利に働かないように計算されることになりました。
ただし、すべての寄付金が該当するわけではないため、一定の要件を満たす寄付金に該当するか否か留意が必要です。
(例としては、受けた寄付金をそのまま研究助成に充てるような内容の寄付金で、事前に行政庁の確認を受けた寄付金となります。)
3.一般的なデメリット・行政庁による監督
(1)定期提出書類の提出
公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに事業計画・予算等を行政庁に提出する必要があります。
また、公益法人は、毎事業年度経過後3カ月以内に事業報告・決算書類等を行政庁に提出する必要があります。当該提出書類の中には、公益認定申請時とほぼ同様の書類が含まれております。
(2)定期的な立入検査
公益法人は、概ね3年に1度は行政庁の立入検査を受けることになります。
(3)変更手続
公益法人は、一定の事由が発生した場合、行政庁に対して変更手続を行う必要があります。
| 変更届出 | 変更後に遅滞なく、届け出る手続き(例:役員変更・代表者変更等) |
| 変更認定 | 変更前に行政庁の認定を受ける手続き(例:事業内容の変更) |
特に変更手続で重要となるのは、変更認定です。変更認定は、公益認定時とほぼ同様の申請書類を作成し、公益認定時と同様に行政庁の審査を受ける必要があります。変更手続を経ることなく、変更を行った場合は厳しく罰せられる可能性があります。
変更認定として特に留意すべき事項は、事業内容の変更です。新規の事業を立ち上げる場合、既存の事業を廃止する場合等、事業内容を変更する場合は、原則として変更認定となります。当該事業の内容の変更は、公益目的事業に限らず、収益事業・共益事業の変更も含まれるので注意が必要です。なお、受益の対象・規模が拡大する等、事業の公益性の判断が明らかに変わらない場合は、変更認定ではなく、変更届出となります。
年度によって事業内容を変更する可能性が高いような場合は、その都度、公益認定と同様の申請・審査が必要となるため、公益法人で運営するのは大変であるといえます。
他方、毎年ほぼ同様の事業内容で法人運営しており、事業内容を変更する可能性があまり高くない場合は、公益法人で運営したとしても、変更手続をあまり気にする必要はありません。
そのため、事業内容の変更可能性は、公益認定を目指す上で重要な判断指針の一つといえます。
4.一般的なデメリット・認定法の規制
(1)社員資格の得喪
公益社団法人は、社員資格の得喪に不当に差別的な条件を付してはなりません。
法律上の構成員である社員と一般的な会員制度上の会員は、イコールではないケースが多いです。一般的な会員制度においては、正会員・賛助会員・名誉会員・学生会員等複数の種別が設定されており、その中で正会員のみを法律上の社員として位置付けているケースが多いです。
さらに、正会員=法律上の社員とすると、社員数が膨大となり、社員総会の運営が困難となるケースにおいては、正会員の中からさらに法律上の社員を選出し、代議員=法律上の社員として位置付けしているケースがあります。
(代議員という名称ではなく、評議員という名称を使用しているケースもあります。評議員という名称は、本来、財団法人の制度のことをいいますが、社団法人において、任意に名称だけ使用しているケースもあります。)
代議員の選出にあたっては、選挙によって行う方法が一般的であり、内閣府のモデル定款・定款上の留意事項において定められた方法に従って、代議員の選出を行っているケースが多いです。
他方、一般社団法人の場合、代議員を選挙によって行わずに選出しているケースがあります(一定の実績のある方を社員総会に推薦し、社員総会において選出しているケース)。
公益社団法人は、社員資格の得喪に不当に差別的な条件を付してはならないという要件があります。そのため、社員となる条件について合理的な条件を付すことは可能です。(例えば、専門性が高い学術団体において、専門家(例えば、医師等)を正会員の要件とすることは全く問題ありません。)
他方、正会員の中からさらに法律上の社員を限定する団体において、内閣府が推奨している選挙の方法以外で選出している場合、当該選出方法が認められるか否かは、個別判断となるため、事前に行政庁と相談しておくのが重要であると考えます。
(2)理事の構成人数の制限
公益社団法人においては、理事の構成人数に関し、親族関係者割合・同一団体出身者割合の制限があります。学術団体において、親族関係者割合が問題となるケースは考えにくいため、留意すべき点は同一団体出身者割合の要件となります。
同一団体出身者割合の制限とは、他の同一の団体の理事・使用人等の割合が理事総数の3分の1を超えてはならないとする制限のことです。なお、他の同一の団体には公益法人は含まれていないため、他の同一の公益法人出身者の割合は問題にはなりません。
学術団体の中には、類似の研究分野の学術団体が数多くあり、そのような場合、理事が類似の学術団体の理事を兼務しているケースが多く見受けられます。そのような場合、仮に兼務先の学術団体が一般法人・NPO法人・任意団体の場合は、当該制限が適用されるため、留意が必要です。
(3)財務3基準 (公益認定申請予算とその後の実績数値について)
公益認定には、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限の3つの財務上の基準があります(財務3基準)。財務3基準は、公益認定の審査時点のみならず、公益認定後も継続して満たすべき基準です。
公益認定の審査時においては、予算ベースで財務3基準を判定します。そのため、財務3基準を満たすような予算を作成すれば、申請書類上は財務3基準を満たしていることになります。また、財務3基準は、ぎりぎりの水準で満たしている場合も余裕の水準で満たしている場合も、満たしていることには変わりありません。そのため、申請書類の予算上、ぎりぎりの水準で財務3基準を満たす形で申請し、公益認定を受けているケースがあります。
他方、公益認定後は、実績ベースで財務3基準を満たす必要があります。公益認定時の申請においては、ぎりぎりの水準で財務3基準を満たすような財務構造の法人の場合、実績ベースにおいては、いずれかの基準を満たさないような状況が生じやすいといえます。そのような場合、財務3基準を満たすように、様々な対策を講じる必要があり、難しい法人運営が求められることになります。実際、財務3基準にあまり余裕がない状況で公益認定を受けた法人の場合、財務3基準を満たすための対策を毎年度検討しているようなケースは多いです。
財務3基準については、特に対策を講じなくても余裕で満たすような財務構造の法人もあれば、特別な対策を講じないと満たすのが難しい財務構造の法人もあります。また、財務3基準のうち、どの基準が満たしやすく、どの基準が満たしにくいのかは、法人の財務構造によってケースバイケースです。
特別な対策を講じないと財務3基準を満たさないような法人の場合、財務3基準は公益法人化すべきか否かの重要な判断指針になるといえます。
上記の通り、一般法人を公益法人化する場合は、一般的に言われているメリット・デメリットを具体的に当該学術団体の状況に当てはめて、本当にメリット・デメリットとなるか否かを慎重に検討することが重要となります。
NPO法人で活動している学会(学術団体)を公益法人化すべきか否か検討する場合、メリット・デメリットを比較検討することになります。
メリットとしては、社会的信頼性の向上と税務上の優遇措置が挙げられます。
他方、デメリットとしては、行政庁の監督下となり、一般法・認定法に定める様々な規制を受けることが挙げられます。(NPO法人は、所轄庁の監督下にありますが、公益法人における行政庁の監督の方がより厳しくなります。)
なお、NPO法人が公益法人となるためには、まず一般法人を設立し、当該一般法人を公益法人化した上で、NPO法人の事業を公益法人に譲渡する必要があります。そのため、NPO法人の公益法人化については、事前の準備と行政庁の審査を合わせて年単位で時間がかかるのが一般的です。また、公益法人が一般法人に戻る場合、公益的な財産を国等に贈与しなければなりません。そのため、公益法人化すべきか否かは、慎重に検討する必要があります。
1.一般的なメリット・社会的信頼性の向上
一般的に公益法人は、社会的信頼性が高い法人といえます。他方、学術団体の場合、法人形態にかかわらず、社会的信頼性が高いケースが一般的です。そのため、改めて対外的に公益法人の肩書きが重要となるのはそれほど多くないかもしれません。
2.一般的なメリット・税務上の優遇措置
(1)寄付金の優遇措置
公益法人は、寄付する側にとって税制上の優遇措置があるため、寄付を受けやすくなるというメリットがあります。他方、法人の財源として、寄付金収入がそれほど重要でないケース、寄付金の優遇措置の有無に関係なく、寄付金が集まるケースがあるため、寄付金の優遇措置が学術団体にとってメリットとなるか否かはケースバイケースであると考えます。
(なお、NPO法人のうち、認定NPO法人(仮認定NPO法人)の場合は、公益法人とほぼ同様の寄付金の優遇措置があるため、当該優遇措置はメリットにはなりません。)
(2)源泉所得税の優遇措置
公益法人は、利子等の源泉所得税が非課税となります。そのため、基本財産・特定資産等の運用益が大きい団体にとって、非課税措置となるか否かは、税務上重要となります。
他方、基本財産・特定資産等の運用益がそれほど大きくない団体にとっては、源泉所得税の優遇措置は、それほど重要でないといえます。
(3)法人税法上の優遇措置
公益法人もNPO法人もいずれも法人税法上の収益事業のみ課税されますが、公益法人の場合、より収益事業の課税範囲が限定されます。また、公益法人に関しては、収益事業から生じた利益を公益目的事業に繰入した場合、みなし寄付金が適用され、課税所得計算上、有利となります。
他方、学術団体の中には、法人税法上の収益事業を全く行っていないケース、法人税法上の収益事業を行っているが、課税所得がそもそも生じていないケースがあります。そのようなケースにおいては、そもそも法人税が生じていないため、法人税法上の優遇措置はあまり関係ないといえます。
(なお、NPO法人のうち、認定NPO法人の場合もみなし寄付金制度がありますが、認定NPO法人のみなし寄付金は、公益法人のみなし寄付金よりも限定的です。)
(4)消費税の優遇措置
公益法人・NPO法人は、寄付金収入・会費収入等の割合が大きい場合、消費税法上、特別な調整計算を行います。その際、寄付金収入の割合が大きい法人については、調整計算上、不利に働きます。
他方、平成25年度税制改正によって、公益法人の受ける寄付金のうち一定の要件を満たす寄付金に関しては、調整計算上、不利に働かないように計算されることになりました。
ただし、すべての寄付金が該当するわけではないため、一定の要件を満たす寄付金に該当するか否か留意が必要です。
(例としては、受けた寄付金をそのまま研究助成に充てるような内容の寄付金で、事前に行政庁の確認を受けた寄付金となります。)
3.一般的なデメリット・行政庁による監督
(1)定期提出書類の提出
公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに事業計画・予算等を行政庁に提出する必要があります。
また、公益法人は、毎事業年度経過後3カ月以内に事業報告・決算書類等を行政庁に提出する必要があります。当該提出書類の中には、公益認定申請時とほぼ同様の書類が含まれております。
(2)定期的な立入検査
公益法人は、概ね3年に1度は行政庁の立入検査を受けることになります。
公益法人は、一定の事由が発生した場合、行政庁に対して変更手続を行う必要があります。
| 変更届出 | 変更後に遅滞なく、届け出る手続き(例:役員変更・代表者変更等) |
| 変更認定 | 変更前に行政庁の認定を受ける手続き(例:事業内容の変更) |
特に変更手続で重要となるのは、変更認定です。変更認定は、公益認定時とほぼ同様の申請書類を作成し、公益認定時と同様に行政庁の審査を受ける必要があります。変更手続を経ることなく、変更を行った場合は厳しく罰せられる可能性があります。
変更認定として特に留意すべき事項は、事業内容の変更です。新規の事業を立ち上げる場合、既存の事業を廃止する場合等、事業内容を変更する場合は、原則として変更認定となります。当該事業の内容の変更は、公益目的事業に限らず、収益事業・共益事業の変更も含まれるので注意が必要です。なお、受益の対象・規模が拡大する等、事業の公益性の判断が明らかに変わらない場合は、変更認定ではなく、変更届出となります。
年度によって事業内容を変更する可能性が高いような場合は、その都度、公益認定と同様の申請・審査が必要となるため、公益法人で運営するのは大変であるといえます。
他方、毎年ほぼ同様の事業内容で法人運営しており、事業内容を変更する可能性があまり高くない場合は、公益法人で運営したとしても、変更手続をあまり気にする必要はありません。
そのため、事業内容の変更可能性は、公益認定を目指す上で重要な判断指針の一つといえます。
4.一般的なデメリット・一般法、認定法の規制
(1)役員の選任
NPO法人の場合、定款の定めによっては理事会でも役員を選任することが可能ですが、公益社団法人の場合、必ず社員総会で役員を選任する必要があります。
(2)理事会の運営
NPO法人の場合、理事会の運営上、代理人出席・書面決議が可能ですが、公益社団法人の場合、必ず本人出席する必要があります。
(3)理事の構成人数の制限
公益社団法人においては、同一団体出身者割合の制限があります。
同一団体出身者割合の制限とは、他の同一の団体の理事・使用人等の割合が理事総数の3分の1を超えてはならないとする制限のことです。なお、他の同一の団体には公益法人は含まれていないため、他の同一の公益法人出身者の割合は問題にはなりません。
学術団体の中には、類似の研究分野の学術団体が数多くあり、そのような場合、理事が類似の学術団体の理事を兼務しているケースが多く見受けられます。そのような場合、仮に兼務先の学術団体が一般法人・NPO法人・任意団体の場合は、当該制限が適用されるため、留意が必要です。
(4)財務3基準 (公益認定申請予算とその後の実績数値について)
公益認定には、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限の3つの財務上の基準があります(財務3基準)。財務3基準は、公益認定の審査時点のみならず、公益認定後も継続して満たすべき基準です。
公益認定の審査時においては、予算ベースで財務3基準を判定します。そのため、財務3基準を満たすような予算を作成すれば、申請書類上は財務3基準を満たしていることになります。また、財務3基準は、ぎりぎりの水準で満たしている場合も余裕の水準で満たしている場合も、満たしていることには変わりありません。そのため、申請書類の予算上、ぎりぎりの水準で財務3基準を満たす形で申請し、公益認定を受けているケースがあります。
他方、公益認定後は、実績ベースで財務3基準を満たす必要があります。公益認定時の申請においては、ぎりぎりの水準で財務3基準を満たすような財務構造の法人の場合、実績ベースにおいては、いずれかの基準を満たさないような状況が生じやすいといえます。そのような場合、財務3基準を満たすように、様々な対策を講じる必要があり、難しい法人運営が求められることになります。実際、財務3基準にあまり余裕がない状況で公益認定を受けた法人の場合、財務3基準を満たすための対策を毎年度検討しているようなケースは多いです。
財務3基準については、特に対策を講じなくても余裕で満たすような財務構造の法人もあれば、特別な対策を講じないと満たすのが難しい財務構造の法人もあります。また、財務3基準のうち、どの基準が満たしやすく、どの基準が満たしにくいのかは、法人の財務構造によってケースバイケースです。
特別な対策を講じないと財務3基準を満たさないような法人の場合、財務3基準は公益法人化すべきか否かの重要な判断指針になるといえます。
上記の通り、NPO法人を公益法人化する場合は、一般的に言われているメリット・デメリットを具体的に当該学術団体の状況に当てはめて、本当にメリット・デメリットとなるか否かを慎重に検討することが重要となります。
学会(学術団体)においては、下記の理由により税務申告を行っていないケースがあります。
・過去一度も税務申告をしていないが、今まで税務調査はなく、税務署等から問合せを受けたこともない。
・源泉所得税の納付は行っているが、それ以外は特に行っていない。特に税務署等から指摘を受けたことがない。
・他の類似の学術団体において税務申告していない。
・営利法人と違って、公益的な事業活動のみを実施している。
・公益法人である、又は任意団体である。
・決算が赤字である。
・学術総会では多額の収入があるが、学術総会の決算は学会本体の決算とは別であり、学会本体自体は、収益事業を行っていない。
上記の理由は、いずれも税務申告を行わなくてよい理由にはなりません。
申告が必要となる税目として代表的なものは、法人税・消費税があります。
申告義務の有無は、それぞれの税目ごとに、それぞれの要件に基づいて判定する必要があります。
そのため、法人税・消費税、いずれも申告が必要なケースもあれば、いずれも申告不要なケースもあります。また、法人税のみ又は消費税のみ申告が必要なケースもあります。
いずれの税目について、申告義務があるのかについては、当該団体の事業内容・事業規模によって異なるため、個別具体的な検討が必要となります。