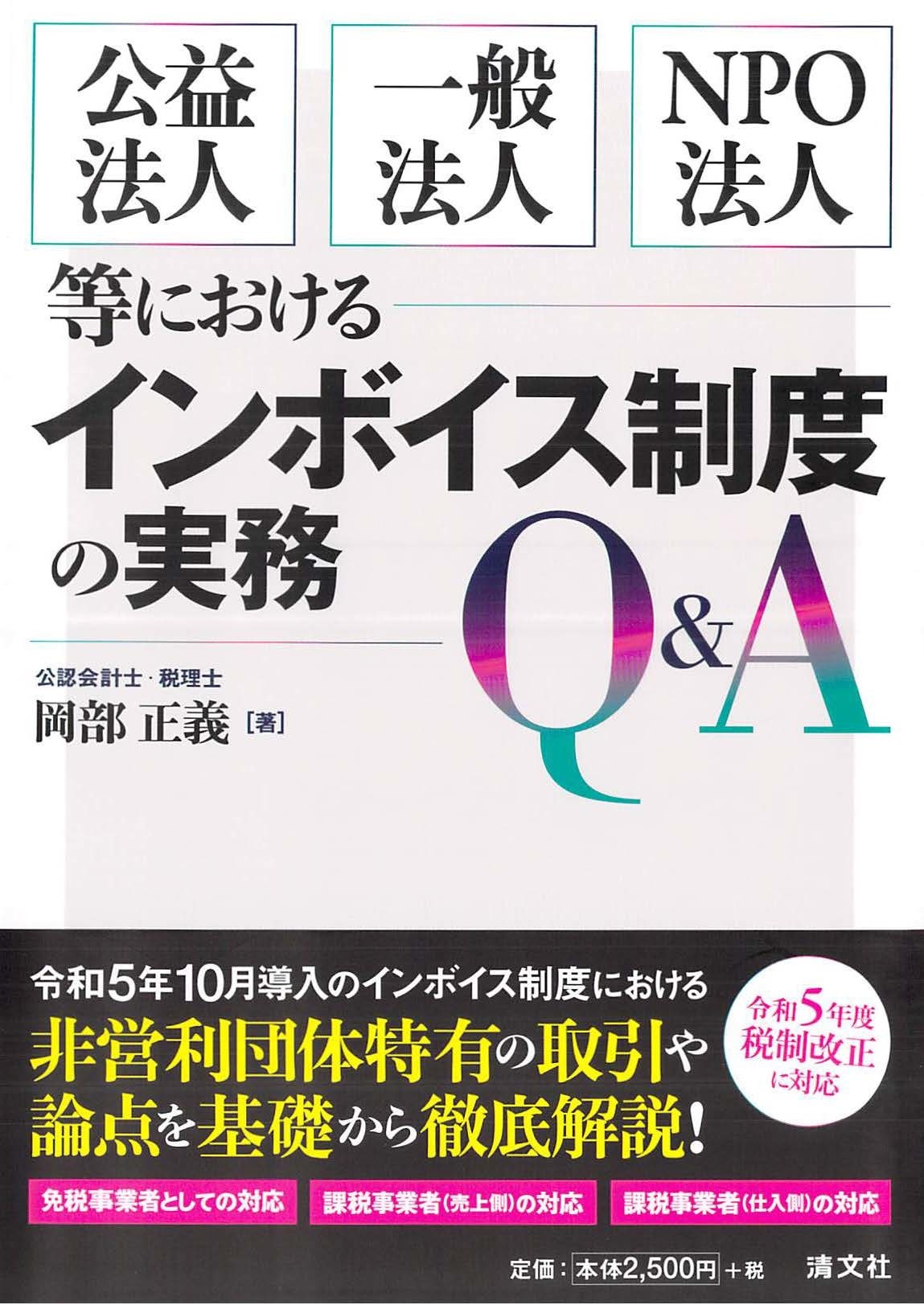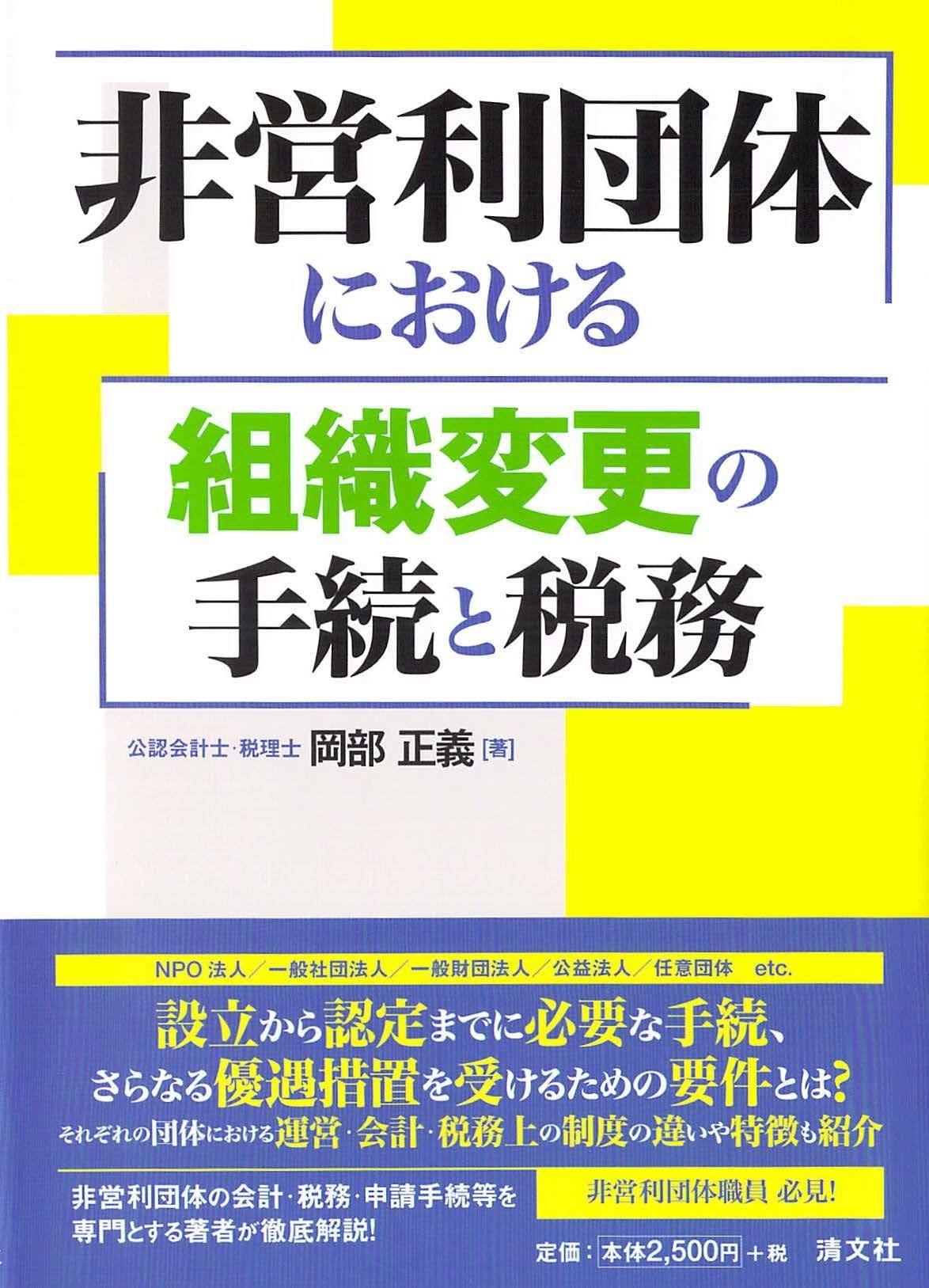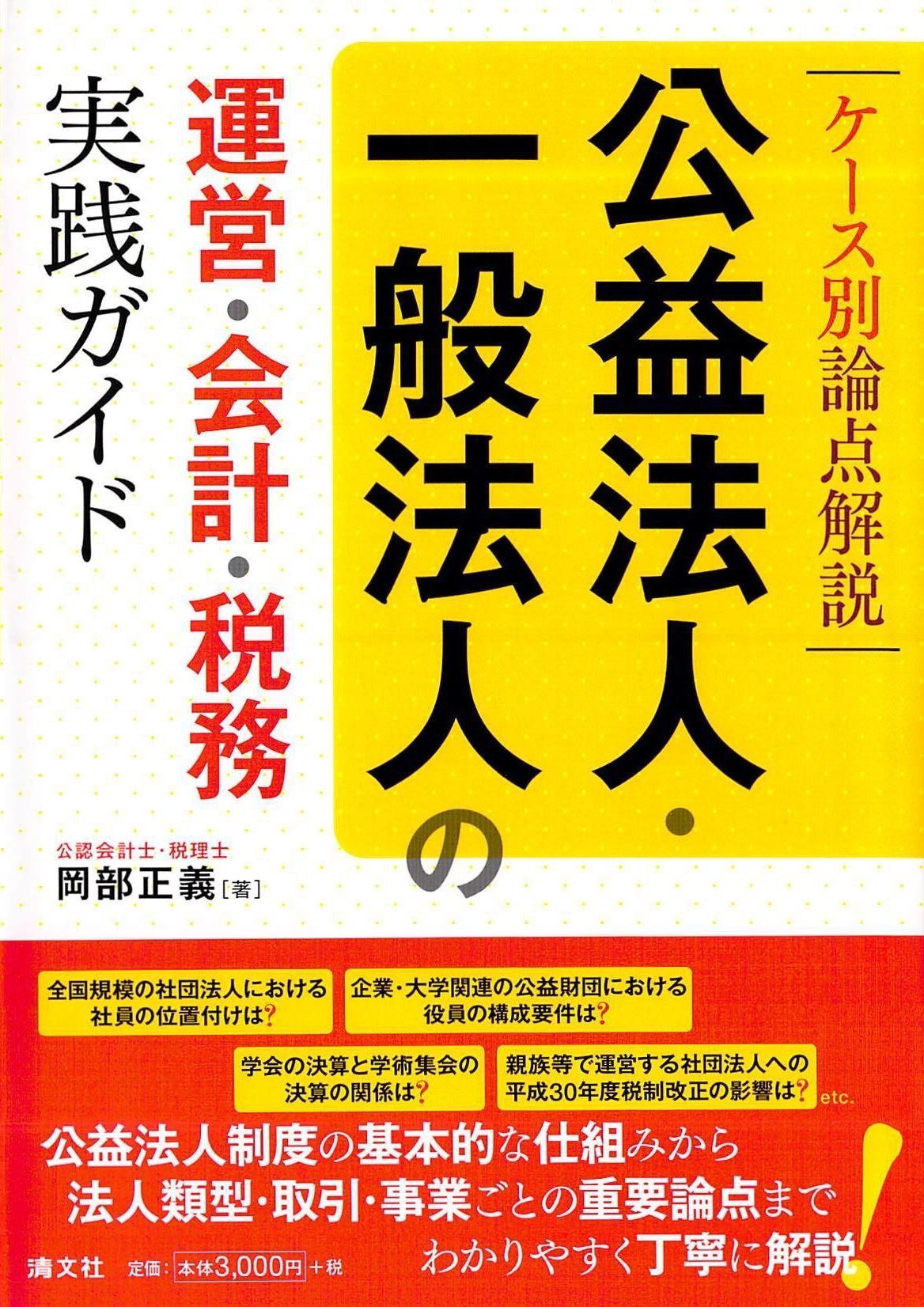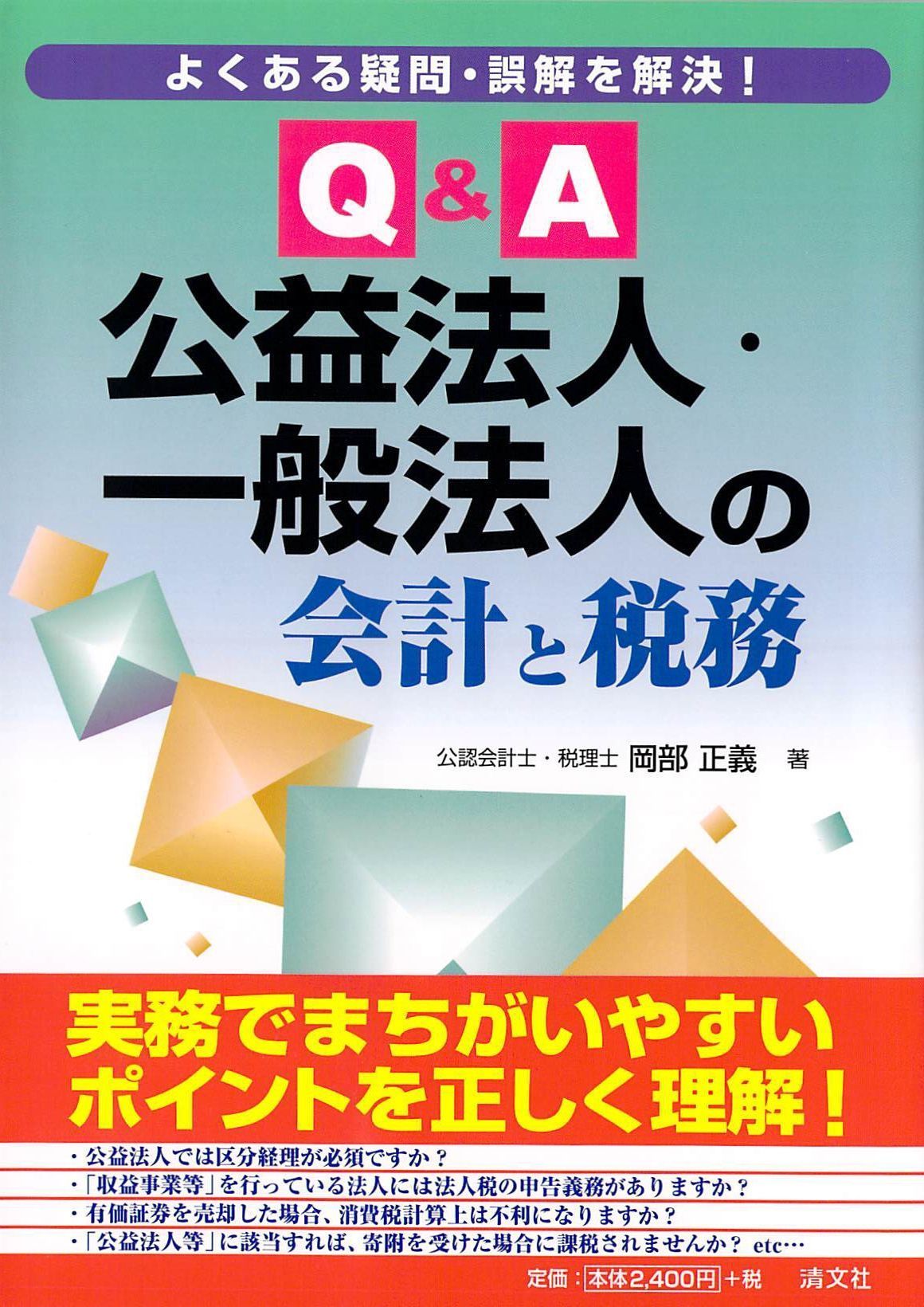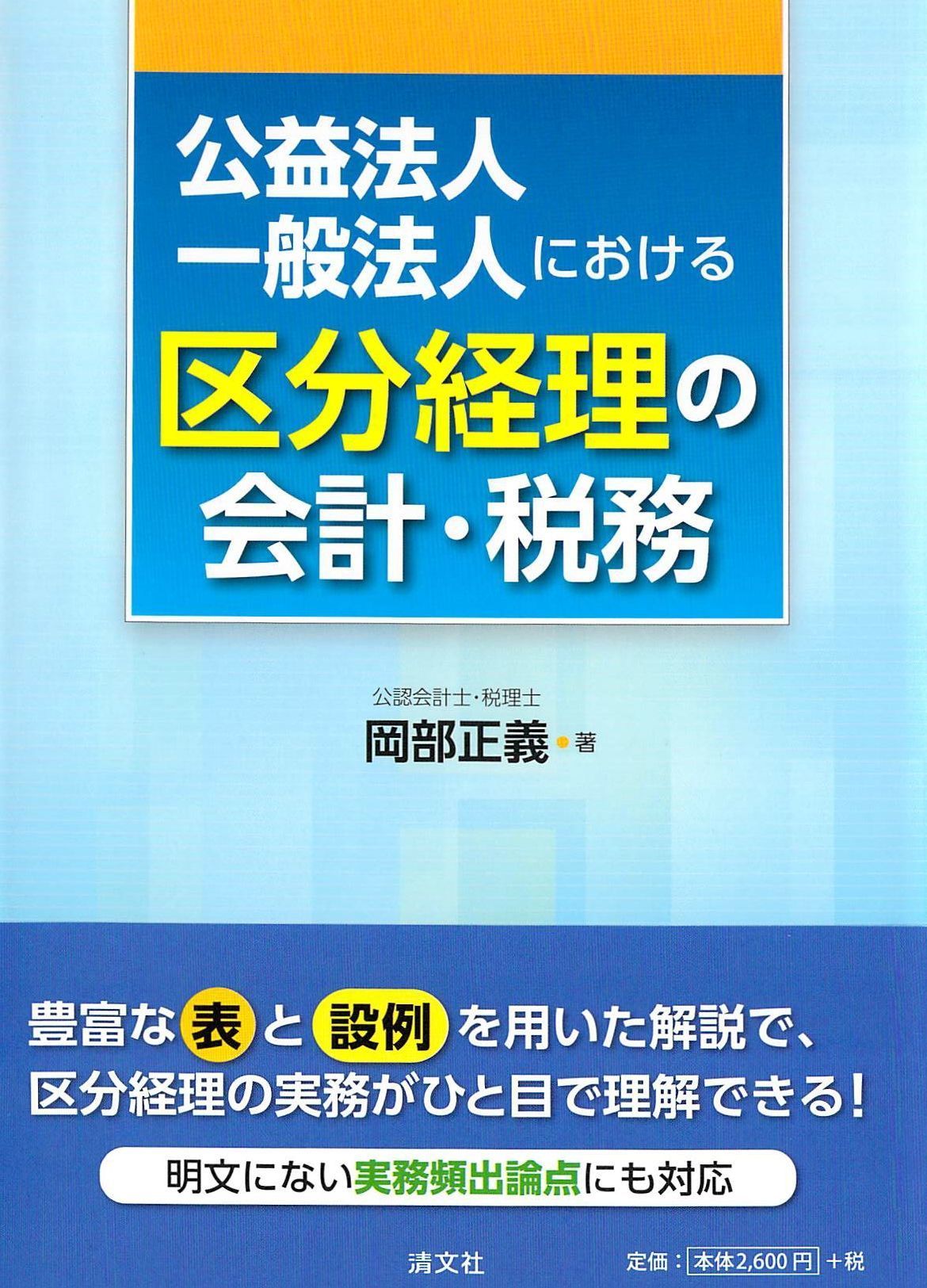公益認定のポイント
公益法人へ移行する際のポイントを解説いたします。
公益法人は、税制上の様々な優遇措置が認められております。
1.法人税法上の優遇措置
(1)収益事業課税
公益法人は、税法上定められた34の事業のみ課税されます(収益事業課税)。非営利型の一般法人も収益事業課税ですが、一般法人の場合は税務調査により非営利性を否認されるリスクがあり、収益事業課税が絶対ではありません。他方、公益法人の場合は公益法人である限り、必ず収益事業課税となります。
また、公益法人の場合は税法上定められた34の事業であっても、認定法上の公益目的事業に該当する場合は収益事業の範囲から除外されることになっています。そのため、同じ収益事業課税であっても、非営利型の一般法人の収益事業課税よりも、公益法人の収益事業課税の方が課税の範囲が限定的であるといえます。
(2)みなし寄付金
みなし寄付金とは、収益事業から公益目的事業に対して利益の繰入計算を行った場合、法人内の資金移動にもかかわらず、寄付金とみなして計算することができる制度のことをいいます。すなわち、みなし寄附金を利用すれば、収益事業から生じた課税所得を圧縮することが可能となります。利益の繰入額を100%とした場合、状況によっては課税所得の大部分を圧縮することが可能です。
2.源泉所得税法上の優遇措置
受取利子・配当等に係る源泉所得税が非課税となります。
3.寄付金優遇税制
寄付が集めやすいように様々な寄付金優遇税制が認められています。
(1)個人の寄付における所得控除・税額控除
公益法人に対する個人の寄付については、所得控除することが可能です。また、一定の要件を満たした法人が申請手続すると、所得控除の他、税額控除も選択で認められます。
①所得控除 (すべての公益法人で適用可能。)
所得金額から「寄付金(所得金額の40%が限度)−2,000円」を控除することができます。
②税額控除 (一定の公益法人で適用可能。)
税額から「寄付金(所得金額の40%が限度)−2,000円」×40%(税額の25%が限度)を控除することができます。
(2)法人の寄付における所得控除
一般寄付金の損金算入限度額の他、別枠で特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が認められています。
公益法人の特別損金算入限度額=(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2
(3)譲渡所得の非課税措置
通常、含み益を有している資産を法人に寄付した場合、含み益に対して、みなし譲渡所得が発生します。
ただし、租税特別措置法40条の要件を満たしている場合、公益法人に対して寄付した財産のみなし譲渡所得を非課税にすることができます。
(4)相続税の非課税措置
通常、相続財産を法人に寄付した場合、相続財産の課税を受けることになります。
ただし、租税特別措置法70条の要件を満たしている場合、公益法人に対して寄付した相続財産を非課税にすることができます。
4.その他税制上の優遇措置
そのほか、一定の要件を満たした場合、均等割の非課税措置、固定資産税の非課税措置等が認められています。
一般社団法人・一般財団法人(一般法人)は、公益認定を受けることにより、公益社団法人・公益財団法人(公益法人)となることができます。
公益認定を受けるためには、行政庁に公益認定申請を行い、審査を受ける必要があります。
行政庁は、全国展開している法人であれば内閣府となり、各都道府県のみで活動している法人であれば、各都道府県となります。
なお、任意団体が公益法人化する場合は、まず一般法人化し、その後に公益認定の申請を行う必要があります。
公益法人は、公益目的事業を実施する法人です。 公益目的事業とは、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」をいいます。
法人の実施している事業が公益目的事業に該当するか否かの判定にあたっては、「不特定かつ多数の者」が重要となります。
一般的に会員等の法人内部の者のみを対象としている事業は、「不特定かつ多数の者」を対象としていないため、公益目的事業には該当しません。(ただし、事業の性格上、合理的な参加の要件を定めることは認められています。)
そのため、会員限定等の事業を公益目的事業に位置付けようとする場合は、会員限定の撤廃等の検討を行う必要があります。
公益法人となるためには、認定法に定められた18項目を満たす必要があります。18項目の中には、単に定款に記載するだけという項目もあれば、法人の財務構造、法人の組織運営方法について一定の要件を求める項目もあります。以下では、実務上特に重要となる項目について解説いたします。
1.財務3基準
公益法人は、以下の3つの財務上の基準を満たす必要があります。
(1)収支相償
収支相償とは、公益目的事業に係る収入の額が、その事業に必要な適正な費用を償う額を超えてはならないという基準です。基本的な考え方としては、公益目的事業は、公益を目的としているため、儲けてはならないという考え方です。
収支相償の判定は、2段階で行われます。第1段階は、公益目的事業ごとに判定し、第2段階は、第1段階の収支に加えて、会費収入等の公益目的事業全体に係る収入、収益事業等からの利益の繰入額を合算した上で判定することになります。
(2)公益目的事業比率
公益目的事業比率とは、公益目的事業の費用が法人全体の費用の50%以上でなければならないという基準です。公益法人は、公益目的事業を行うことを主としていることが求められており、主として行っているか否かは、費用ベースで判定することになっています。
(3)遊休財産額の保有制限
遊休財産額の保有制限とは、1年間分の公益目的事業の実施に要した費用を超えて遊休財産を保有していはならないという基準です。遊休財産とは、具体的な使途が定まってない遊休状態にある財産のことです。
2.その他の認定要件
上記の財務3基準の他、法人によっては、以下の要件についても注意が必要です。
(1)社員資格の得喪
社団法人の場合、社員となるための資格について、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付してはなりません。社員となるための資格について、一定の要件を設けること自体が認められないわけではありませんが、要件を設ける場合は、その要件の合理性・必要性について審査されることになります。
(2)社員の議決権
社団法人の場合、社員の議決権は、原則として1社員1議決権となります。それ以外の取扱いをする場合は、その理由が審査されることになります。
(3)役員の親族要件・同一団体要件
各理事について、親族関係者の割合が3分の1を超えてはなりません。また、同一団体の理事・使用人の割合が3分の1を超えてはなりません。監事についても同様です。
(4)技術的能力
公益目的事業を実施するにあたっては、法人自ら実施する能力がある必要があります。事業の大部分を丸投げ外注しているような場合、技術的能力がないと判断される可能性があります。
公益認定を受けるためには、申請書類を作成し、行政庁に認定申請した上で、行政庁の審査を受ける必要があります。公益認定に向けた作業としては、以下の通りです。
1.事業区分の検討、事業内容の見直し
どの事業を公益目的事業とし、どの事業を収益事業等とするのか、事業の区分を検討する必要があります。事業によって、公益的な性格と、収益的な性格が混在するような事業の場合は、事業単位自体を見直す必要があります。また、公益目的事業の区分も大きな単位で一つの事業とするのか、小さな単位で一つの事業とするのか検討する必要があります。
また、現在会員限定としているような事業を公益目的事業として位置付けしようとする場合は、受益の対象者を見直す等の事業内容の見直しも行う必要があります。さらに、丸投げ外注をしているような事業を公益目的事業として位置付けしようとする場合、技術的能力の観点から事業の運営方法を見直す必要があります。
事業区分・事業内容の見直しは、財務3基準の観点、税務上の観点、法人の事務負担の観点等、複合的な観点で検討する必要があります。
2.財務3基準の検討、会計処理及び財務構造の見直し
1で定義した事業区分に基づいて財務3基準を満たすか否か確認する必要があります。財務基準を満たすか否かにあたっては、短期的に満たすことができるだけなく、長期的に満たすことができるか否かが重要となります。なぜなら、公益認定の審査時には、1年度分の予算に基づいて財務基準を満たしているか否か判断されますが、公益法人移行後は、決算数値に基づいて、毎期財務基準を満たしているか否かが判断されるからです。
なお、財務基準の判定上の事業費については、直接費用だけでなく、人件費等の共通費用も一部事業費として配賦計算することが可能です。仮に、従来の会計処理上、共通費用を配賦計算していない場合は、会計処理の方法についても見直す必要があります。
財務基準を満たしていない場合、財務構造の見直しを行うか、事業区分自体を再度見直ししていく必要があります。
3.定款・諸規程の見直し、その他の認定基準の確認
認定基準の中には、定款の記載に関係する認定基準があります。そのため、公益認定のタイミングで定款を変更する必要があります。また、申請書類には、役員報酬規程・会員規程等を添付する必要があるため、必要に応じて諸規程を見直しすることになります。さらに、役員の親族要件・同一団体出身要件等、その他の認定基準についても確認しておく必要があります。
4.事業計画・収支予算書の作成
申請書類は、申請日以降の事業年度の事業計画・収支予算書に基づいて作成する必要があります。そのため、財務3基準を満たす形で収支予算書を作成する必要があります。
5.申請書類の作成
4の事業計画・収支予算書に基づいて申請書類を作成します。申請書類は少なくとも理事会等の法人の意思決定を経た上で提出する必要があります。
6.公益認定の審査・答申
行政庁に申請書類を提出し、公益認定の審査を受けます。公益認定の審査は、原則として4カ月以内となっておりますが、事業規模・事業内容の複雑性等によって、長期間になる場合もあります。
7.公益認定の処分
公益認定の審査を受け、委員会から答申が出た場合、行政庁から公益認定の処分を受けることになります。公益認定の処分をもって、公益法人となります。
公益認定を受けるための事業区分・法人運営のかたちは、必ずしも一つだけではありません。とりあえず、認定基準の充足のみを考えて、公益認定を受けると、その後の法人運営で支障が出るケースもあります。そのため、公益認定にあたっては、複合的な視点で検討を進めることが重要です。
1.長期的な視点
公益認定時には、1事業年度の予算数値をもとに財務基準の充足性が判断されますが、公益認定後は、決算数値をもとに財務基準の充足性が判断されることになります。
短期的には、財務基準を満たすことが可能であったとしても、長期的には、満たすことが難しいケースもあります (たとえば、短期的に公益目的事業の支出を増加させれば、収支相償・公益目的事業比率を満たすことが可能であっても、長期的には法人全体の資金がもたないようなこともあります)。
そのため、公益認定の際には、長期的な視点で財務基準を満たすような事業区分及び財務構造を検討していく必要があります。
2.会員の意向
社団法人は一般的に会員制度を設けています。また、財団法人でも会員制度を設けているケースは数多くあります。そして、会員制度を設けている法人の場合、会費収入が法人にとって重要な収入となっているケースが多いです。
公益目的事業の要件である「不特定かつ多数の者」を満たすために、従来、会員のために行ってた会員限定事業の会員限定を撤廃すると、会員となるメリットが減少し、会員の増加・維持が困難になるケースも想定されます。
認定基準を満たそうとする場合、単純に会員限定の撤廃をするだけではなく、他の方法(たとえば、他の公益目的事業の規模を拡大する等)で、認定基準を満たすことができないか検討していくのが重要であるといえます。
3.税務上の視点
公益法人は収益事業課税となります。税法上の収益事業とは、税法上定められた34の事業(公益目的事業を除く)のことをいいます。他方、認定法上の収益事業等は、公益目的事業以外の事業のこといいます。税法上の収益事業と認定法上の収益事業等は、全く異なる定義であるため、切り離して考える必要があります。
たとえば、一般教養関係のセミナー・講習会で収益を上げ、当該事業を認定法上の収益事業として位置付けていたとしても、法人税法上は収益事業に該当しません。他方、不動産賃貸で収益を上げ、当該事業を認定法上の収益事業として位置付けている場合、法人税法上も収益事業に該当します。このように、認定法上の収益事業と税法上の収益事業が一致しないケースと一致するケースが存在します。
そのため、認定法上の観点からのみ公益目的事業・収益事業等を分類するのではなく、税法上の観点からも税法上の収益事業を分類しておく必要があります。
公益法人の収益事業課税においては、税法上定められた34の事業であったとしても、公益目的事業に該当する場合、収益事業から除外することになっています。なお、収益事業から除外されることは必ずしも税務上有利になるわけではありません。たとえば、赤字の事業が収益事業から除外された場合、他の黒字と相殺できなくなる分だけ不利になるケースもあります。
また、公益法人の収益事業課税においては、みなし寄付金が認められており、収益事業から生じた課税所得を圧縮することが可能となっております。当該みなし寄付金の計算は、認定法上における収益事業等からの利益の繰入計算の方法と基本的な考え方は整合しておりますが、上記の通り、認定法上の収益事業等と税法上の収益事業は必ずしもイコールでない点、計算書類における収益・費用と税法上の益金・損金は必ずしもイコールでない点等から、必ずしも計算結果が一致するわけではありません。
税務上の視点を考慮せず、認定基準の観点のみで事業区分の検討を行った場合、公益認定後に思わぬ税務負担が生じる可能性もあります。そのため、税負担を最小限に抑えた形で認定基準を満たすように検討していく必要があります。
4.法人運営上の視点
公益認定後は、事業内容を変更する場合は、変更認定・変更届出の手続きが必要となります。特に、変更認定に該当した場合、公益認定時と同様の申請書類を作成し、行政庁の審査を受けなければなりません。
公益認定の申請時の事業区分の方法、事業概要の説明によっては、事業内容を多少変更する場合であっても、その都度変更認定が必要になるケースが出てきます。
今後の法人運営の方向性を踏まえた上で、幅広い観点から事業区分の定義、事業概要の説明を行い、可能な限り、変更認定を行うことなく、法人運営ができるように工夫して公益申請するのが望ましいといえます。
上記の通り、公益認定にあたっては、複合的な視点で検討するのが重要であるといえます。当事務所は、公益法人に特化した公認会計士・税理士・行政書士の事務所であるため、会計面・税務面・申請手続面の複合的な視点から公益認定の作業をサポートしております。単に認定基準を満たすだけではなく、会員の方の意向に最大限沿った形で長期安定的に認定基準を満たし、かつ税務上の負担も少ない形の公益認定を受けられるようにサポートしております。